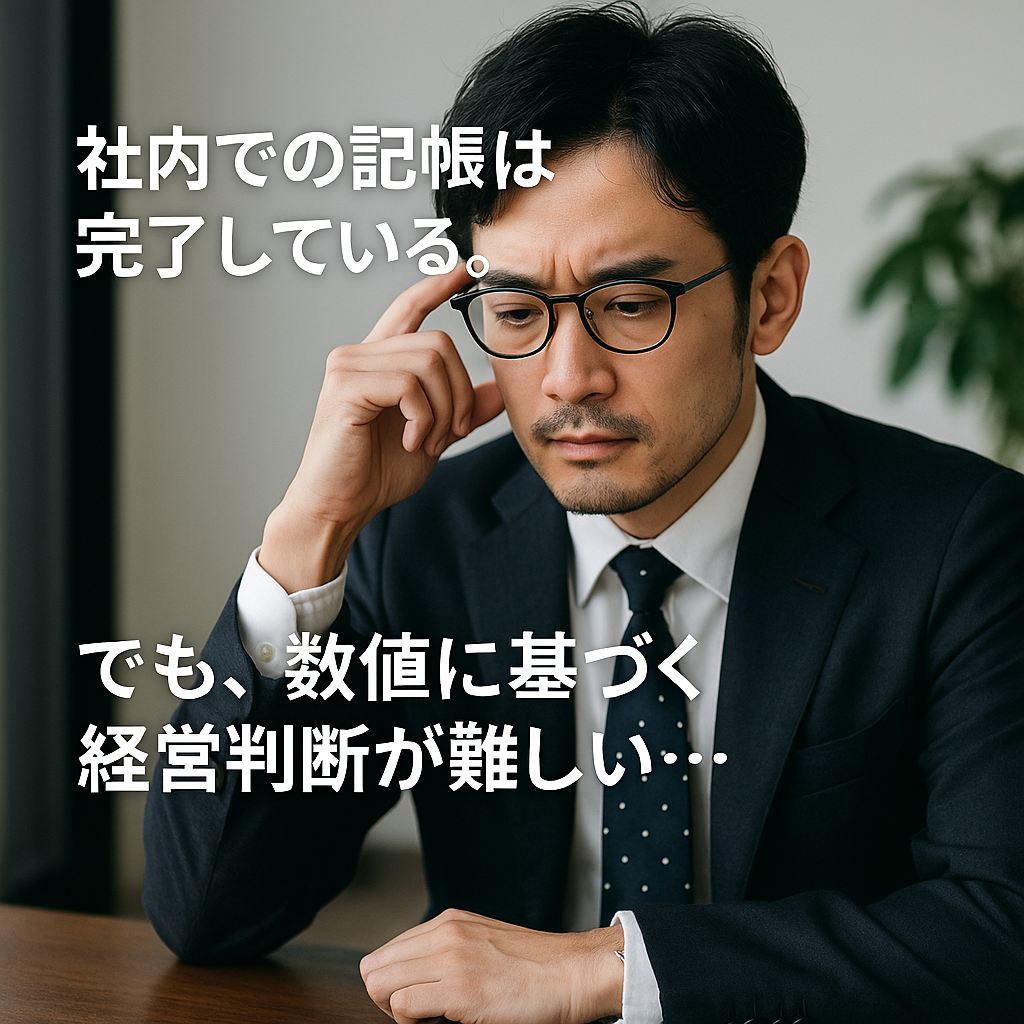
目次
【はじめに】
経理担当者が日々きちんと記帳を行い、月次の試算表もタイムリーに提出されている──。
そのように「経理体制が整っている会社」は、増えてきています。
しかし、社長の立場から見たときに、
「経理データはあるけど、それをどう経営に活かせばいいのか分からない」
「報告は受けているけど、次の判断材料になっていない」
といった“情報の使い方”に悩む声は、まだまだ多く聞かれます。
これは、「経理の正確性」と「経営判断に使える情報」との間にあるギャップが原因です。
そこで、今回は、社内の経理データを、“記録”から“経営判断に使える情報”にするための3つの視点をご紹介します。
【1. 過去を見るだけでなく、「未来を読む」データへ】
多くの経理データは、「過去の記録」に基づいています。
例えば、損益計算書は「今月いくら儲かったか」、貸借対照表は「現在どのような資産・負債構造か」を表すものです。
もちろん、これらは会社の現状を把握する上で非常に重要な情報ですが、
経営判断においては「未来をどう予測するか」という事も求められます。
ここで役立つのが、
・資金繰り表
・損益予測表
・キャッシュフロー予測
といった“未来志向の資料”です。
例えば、次のように応用します:
-
過去3ヶ月の売上推移と入金サイトをもとに、来月以降の現金残高を予測
-
固定費と変動費を分解して、損益分岐点を算出
-
今後の設備投資予定を織り込んだ資金計画を立てる
このように、経理データを「未来の経営判断」に転用することで、社長が“今すべき意思決定”が明確になります。
【2. 数字を「図解」することで“伝わる資料”に変える】

経理データに関し、多忙な社長がすべての数字を読み解くのは現実的ではありません。
だからこそ、数字の「見せ方」に工夫が必要です。
例えば、
・収支の月別推移を折れ線グラフで示す
・部門別の利益構成を円グラフにする
・資金残高の月次見通しを棒グラフにする
こうしたビジュアル化によって、「今、何が起きているのか」「どこに課題があるのか」を直感的に理解できるようになります。
数字は“正確”であることに加えて、“伝わる”ことが求められます。
この「伝わる工夫」があるかどうかが、経理データの「活きた情報」としての価値を左右するのです。
【3. 「何を見るか」を社長と経理で共有する】
経理担当者は、日常業務に追われている中で、「社長が何を判断材料にしているか」に気付けていないケースが少なくありません。
逆に、社長側も、「何を報告してほしいか」を明確に伝えていない場合もあります。
このすれ違いを防ぐためには、社長と経理との間で、
-
どの指標に注目すべきか(売上高?利益率?資金残高?)
-
どのタイミングで報告を受けたいか(毎月?隔週?重要イベント前?)
-
どのような形式で見たいか(グラフ?表?コメント付き?)
といった「情報の取り扱いルール」を共有しておくことが重要です。
例えば、次のような運用が考えられます。
・毎月第1週に、前月の資金繰り表を提出
・翌月末時点の現金残高見通しをコメント付きで提示
・前年比・前月比での分析コメントを追加
・社長が注目している「広告費対売上」の比率を毎回報告 など
このように、社長の“経営視点”と、経理担当者の“実務視点”をつなげるルール作りこそ、
経理データを「経営判断のための情報」に変えるカギとなります。
【まとめ】

経理がしっかりしている会社こそ、次に目指すべきは「数字の活用」です。
-
過去から未来へ視点を広げる
-
数字の“見せ方”を工夫して、判断に使いやすくする
-
経営者と経理担当者の間で、“見るべき数字”を共有する
この3つの視点があれば、記録としての経理データが、“経営の道しるべ”として機能するようになります。
「経理担当者の報告はあるけど、私の判断に迷いが残る」
「社内で集計した経営資料はあるけど、金融機関への説明に自信がない」
そう感じる経営者の方は、ぜひ一度、社内の経理データの“活かし方”を見直してみてはいかがでしょうか。
弊所では、社内経理体制を活かした「経営の見える化」のサポートも行っています。
数字は、読み方ひとつで大きな力になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
佐藤経営税務会計事務所
代表税理士 佐藤充宏
東京都江東区亀戸2-39-8米田ビル201号室
e-mail:satokeieitaxact@kbe.biglobe.ne.jp
お問い合わせは、こちらからお気軽にお願い致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー





