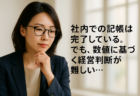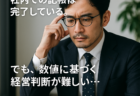目次
1. はじめに
2025年7月、政府がガソリン税の「旧暫定税率」を年内に廃止する方針を示し、大きな注目を集めています。
これは、1リットルあたり25.1円分の暫定課税分を撤廃するという、企業活動や消費者の家計にも影響を及ぼす重要な税制改正です。
しかし、この報道の中であまり語られていないのが「軽油」に対する税負担です。
建設業や運輸業、農業といった業界では、ガソリンではなく軽油が主な燃料として使われており、その税率構造も異なります。
そこで、今回は、軽油に課されている税金の仕組みや暫定税率の有無、そして将来的な税制改正の可能性について、
業界関係者や経営者、そして経理担当者の方に向けてわかりやすく解説します。
2. 軽油税の構造とは?本則+特例の二重構造
軽油にかかる代表的な税は、「軽油引取税」です。
軽油(ディーゼル)を用いるバス・トラックなどの自動車は大型のものが多く、
ガソリンを用いる乗用車と比べても、道路に与えるダメージが大きいとされています。
そこで、地方の道路を整備する費用をまかなうための目的税としてスタートしましたが、その後、
道路に関する費用に限らない財源となりとして、現在は一般財源となっています。
この軽油引取税の本則税率は、1リットルあたり15円です。
しかし、実際には、それに加えて特例税率(いわゆる暫定税率)が上乗せされており、
現在の課税水準は32.1円/Lとなっています。
つまり、本則の2倍以上の水準となっているのが現状です。
逆に、軽油引取税部分には消費税は課税されないという特徴もあります。
こうした税体系は、事業者がコスト管理を行ううえで無視できない項目となっています。
3. 軽油税にも「暫定税率」はあるのか?
あります。
軽油引取税は、本則15円/Lに対して、17.1円の特例(旧暫定税率)部分が上乗せされています。
この構造はガソリン税と非常に似ていますが、異なるのは課税主体が地方自治体であることです。
ガソリン税は国税であり、政治の動きによって迅速に変更が行われることもあります。
一方で、軽油引取税は地方税のため、税率改正には地方の同意や財源調整が必要であり、ハードルが高いとされています。
この点が、2025年夏に報じられた「ガソリン税の旧暫定税率廃止」の対象から、軽油引取税は外れた理由とも考えられています。
4. まとめ

軽油引取税には、暫定税率が組み込まれていますが、現時点ではその廃止は見送られています。
軽油を使う業種にとって、税負担は単なる経費ではなく、事業継続性にも関わる重要な要素ですので、
健全な財務運営と経営判断のため、軽油引取税の今後の動向をチェックしましょう。