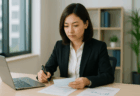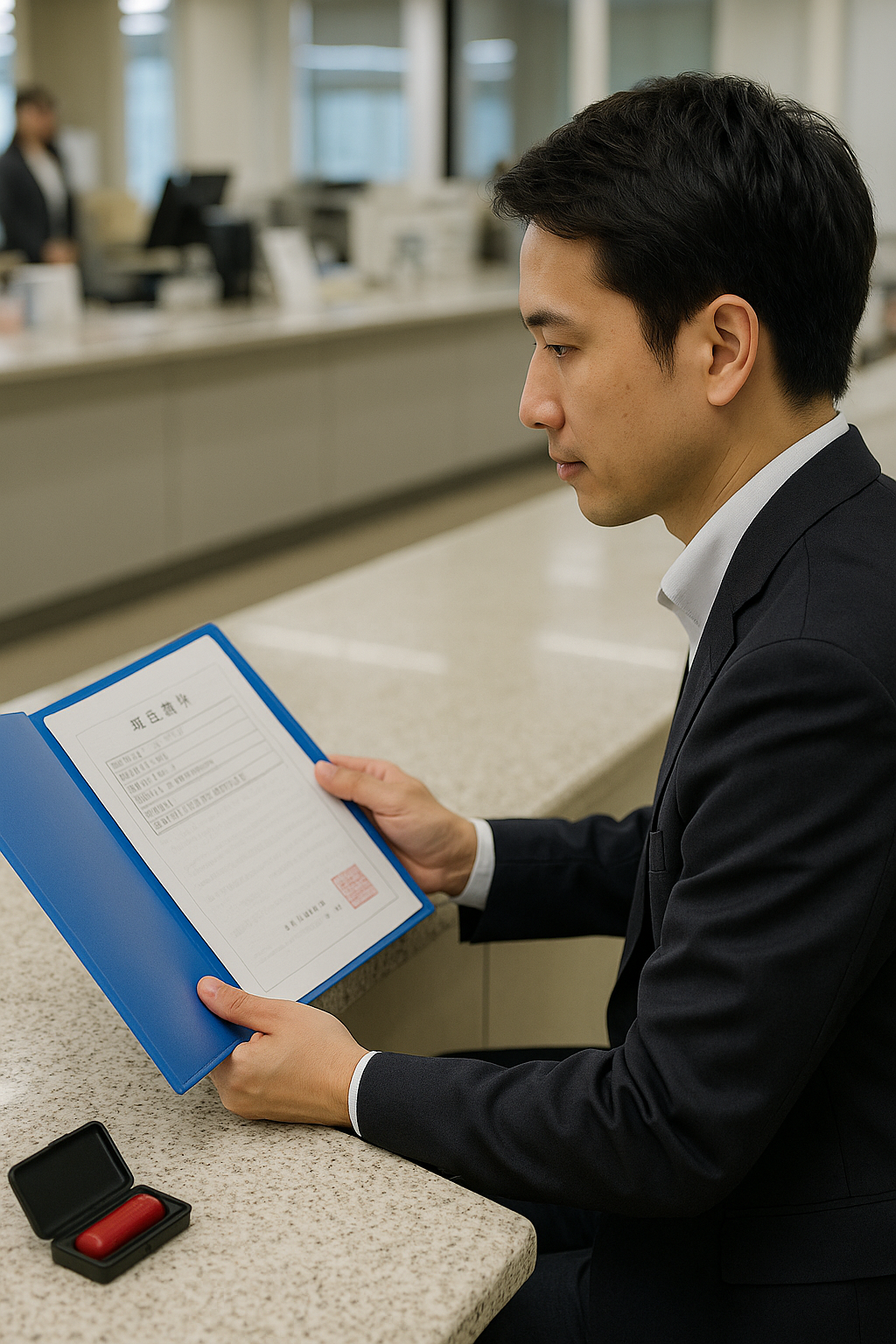
目次
はじめに
会社経営や日常生活において、契約や登記手続きなどの場面で「印鑑証明書」が必要となることは少なくありません。特に会社が金融機関と融資契約を結ぶ際や、不動産の売買契約を行う際には、法的な裏付けとして印鑑証明書の提出が求められます。
このとき必ず発生するのが「印鑑証明手数料」です。金額としては数百円程度ですが、経理処理を行う際には「この手数料に消費税は課税されるのか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、印鑑証明手数料の仕組みや支払方法、経理処理上のポイント、さらに消費税の取り扱いについて整理し、実務上の注意点をわかりやすく解説します。

印鑑証明書とは?
印鑑証明書の基本的な役割
印鑑証明書とは、市区町村に届け出た「実印」が本人のものであることを証明する公文書です。
法人の場合、法務局に届け出た「会社代表者の印鑑」が対象となり、その印影が登記事項として確認できることを証明します。
契約書に押印された印影が、役所や法務局に届け出られている印影と同一であることを確認するために発行されるものであり、取引の安全性を担保する役割を果たします。
会社での利用例
- 金融機関での融資契約
- 不動産売買
- 会社設立登記 他
印鑑証明手数料の内容
発行手数料の標準的な金額
印鑑証明書を取得する際には、都道府県・市区町村の条例に基づいて「印鑑証明手数料」が定められています。
一般的には 1通あたり300円程度 が多く、役所の窓口での発行、コンビニ交付サービスを利用する場合で金額が異なる場合があります。
法人印鑑証明の場合は、法務局での発行となり、現時点では、 1通あたり次の金額です。
・書面で請求:500円
・オンラインで請求(送付で受領):450円
・オンラインで請求(窓口で受領):420円
なお、令和7年4月1日から手数料が改定になりましたので、ご注意ください。
収入印紙・証紙による納付
多くの役所や法務局では、現金のほか、専用の収入印紙や証紙を購入して納付する方法が採用されています。これは「手数料を徴収するための公的な方法」であり、民間のサービス料金とは性格が異なります。
印鑑証明手数料の会計処理
勘定科目の選択
会社で印鑑証明書を取得した場合、通常は次のような勘定科目で処理されます。(手数料や証紙代として計上する場合が比較的多いです)
- 租税公課
- 支払手数料
仕訳の例
例えば、法務局で法人印鑑証明を1通450円で取得した場合の仕訳は以下のとおりです。
(借方)租税公課(又は支払手数料) 450円 / (貸方)現金 450円
消費税の取り扱い
印鑑証明手数料は「非課税」
経理担当者が最も迷いやすいのが、消費税の取り扱いです。
結論から言えば、 印鑑証明手数料の支払いは、「非課税取引」に該当します。
法的根拠
- 消費税法別表第2・五イには、国や地方公共団体が行う「登記・登録・免許・証明」等に係る手数料は 非課税 と明記されています。
- 印鑑証明書の交付は、この「証明」に該当します。
実務上の注意点
1. 経費計上時に誤って課税仕入にしない
会計ソフトに入力する際に、消費税区分を「課税仕入」とせずに、「非課税」として処理する必要があります。
2. 領収証の保存
印鑑証明書の交付を受けた際には、領収証や発行控えを必ず保管しましょう。電子帳簿保存法に対応する場合には、所定の方法により保存しましょう。

まとめ
- 印鑑証明手数料は「行政手数料」の一つであり、消費税法別表第2により 非課税取引 に位置付けられる。
- 会計処理は「租税公課」又は「支払手数料」として計上するのが一般的。
- 会計ソフトでの税区分は「非課税」に設定する必要がある。
少額の支払いであっても、消費税区分の誤りは申告内容の誤りにつながります。経営者及び経理担当者は、行政印鑑証明手数料の「非課税」の根拠を正しく理解し、適正な処理をしましょう。
免責事項
本記事は、印鑑証明手数料に関する一般的な会計・税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は具体的な取引内容や会計方針等によって異なる場合があります。具体的な判断は、必ず税理士等の専門家や所轄税務署等にご確認ください。