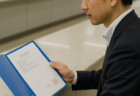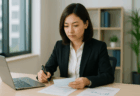目次
はじめに
2025年の日本経済を語るうえで避けて通れないテーマのひとつが「円安インフレ」です。為替市場における円安進行と、国内で続く物価上昇。この2つが重なることで、会社経営には大きな実務的影響が及んでいます。
メディアでは、毎日のように「円安」「インフレ」といった言葉が飛び交いますが、経営現場に身を置く経営者や経理担当者にとって重要なのは、「自社にどのような影響があるのか」「資金繰りや利益確保にどうつなげるのか」といった実務レベルでの判断です。
本記事では、円安インフレが会社経営に与える影響を整理し、経営者や経理担当者が押さえておくべき実務対応のポイントを詳しく解説していきます。

円安インフレとは?仕組みと特徴
円安とは何か
円安とは、為替相場において円の価値が下がり、外国通貨に対して多くの円が必要になる状態を指します。例えば、1ドル=100円だったものが150円になると、同じ1ドルの商品を輸入するために1.5倍の円を支払う必要があります。
円安の要因には、日米の金利差、投資家の資金移動、日本の経常収支等があります。経営者が直接コントロールできるものではありませんが、例えば、輸入をおこなっている企業にとっては、資金繰りに直結する重要な要素です。
インフレとは何か
インフレとは、物価が全体的に上昇することを指します。原材料価格の上昇、エネルギーコストの増加、人件費の上昇など、あらゆるコストが企業経営を圧迫します。
円安とインフレが同時に進むことで、輸入コスト増加+国内コスト上昇という「二重の打撃」が企業に襲いかかります。これが「円安インフレ」です。
円安インフレが会社経営に与える主な影響
1. 調達コストの増加
輸入原材料や部品を使用する製造業、小売業は特に影響を受けます。円安でドル建ての調達費用が上昇し、さらにインフレで国内物流や人件費も増えるため、原価率が上昇。結果として利益率が圧迫されます。
2. 販売価格転嫁の難しさ
本来はコスト増加を販売価格に転嫁すべきですが、競争環境や顧客の価格感度によって簡単に値上げできないケースも多いです。価格転嫁が進まないと、売上額が変わらない状況でも、利益が減少します。
3. 人件費・光熱費の上昇
インフレは従業員の生活コストを引き上げ、賃上げ要求につながります。さらに、電気・ガスなどの光熱費が高止まりしているため、固定費全体が増加します。
4. 金融機関の融資姿勢への影響
円安インフレの局面では、金融機関も企業の資金繰りに対して、慎重な姿勢を取ります。利益が出ていても手元資金が不足するケースや、価格転嫁が追いつかずに資金繰りが悪化するリスクが高まる場合があるためです。金融機関の目線を意識し、キャッシュフローを明確に示すことが重要です。
実務での金融機関対応
- 円安インフレの影響と対応策を具体的に示し、信頼性を高める
- 単なる「融資依頼」ではなく「計画に基づいた必要性」として説明する
- キャッシュフロー重視の説明で、金融機関の理解を得る
経営判断に必要な視点転換
円安インフレは外部要因であり、完全にコントロールすることはできません。しかし、経営者・経理担当者には次のような視点が求められます。
- 外部環境の変化を受け入れ、内部管理を強化する
- 表面的な数字の増減(名目)だけで判断せず、物価・為替・コスト増等の外部要因を反映した「実質」を見ることで、本当の経営状況を見極める
- リスクを単なる脅威ではなく、改善の契機と捉える

まとめ
円安インフレは、調達コスト・販売価格・人件費・資金繰りなど、会社経営のあらゆる局面に影響を与えます。
このような場合には、為替リスクの備えや価格転嫁の工夫、資金繰り表による今後の先読みをする事が必要になるので、経営者と経理担当者が連携し、円安インフレという環境変化に適切な対応を積み重ねていきましょう。
免責
本記事の内容は、一般的な経営・会計・資金管理等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の会社や個人の状況に対する具体的な助言を行うものではありません。必ず専門家等にご相談のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。