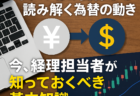【はじめに】
「記帳は正確で、試算表も毎月しっかり出ている」
「経理担当者も優秀で、税理士からも褒められる経理体制がある」
それなのに、
金融機関との面談や融資相談の場になると、思ったように話が進まない──。
このような経験をお持ちの社長様は少なくありません。
これは、決して「経理が間違っている」わけでも、「会社の数字が悪い」わけでもありません。
原因は、「日常の経理データ」と「金融機関が知りたい情報」の間にあるギャップです。
今回は、なぜ社内での記帳が万全でも、金融機関との面談でうまく話が進まないのか、
その理由と改善のヒントを解説します。
目次
【1. 金融機関は“決算書の先”を見ている】
社内経理で作られる月次試算表や決算書は、過去の事実を正確に記録した「過去情報」です。
一方、金融機関が面談や融資判断で重視しているのは、**「これから返済を続けられる会社かどうか」**という未来の視点です。
金融機関の担当者は、次のような問いを頭の中で繰り返しています。
-
今後の売上は安定しているか
-
来月以降、資金がショートする可能性はないか
-
借入金の返済計画は現実的か
-
設備投資や新規事業に伴う資金需要と回収見込みはどうか
もし社長が、試算表や決算書を見せながら「昨年は黒字でした」と説明したとしても、
それだけでは「将来も安心」とは判断されません。
**金融機関が欲しいのは「未来の見通しを裏付ける説明」**です。
ここで必要になるのが、資金繰り表や事業計画書、売上予測といった資料です。
【2. “数字の意味”を社長自身が説明できていない】

経理担当者が作成した資料は正確でも、その数字が意味する内容を社長自身が理解し、
自分の言葉で説明できなければ、面談が思うように進みません。
金融機関担当者は、数字そのものよりも、**「その数字を経営者がどう捉えているか」**を知りたがります。
例えば、売上総利益率が前年より3%下がっている場合──
「なぜ下がったのか」
「今後どう回復させるのか」
「そのために何を実行しているのか」
こうした質問に、即答できる経営者は意外と少ないものです。
ここで大切なのは、経理データを“経営の言葉”に翻訳しておくことです。
数値の変化を事前に分析し、「要因」と「対策」をセットで準備しておけば、面談でも説得力のある説明ができます。
【3. 面談での話題が“数字の読み上げ”だけになっている】
金融機関との面談でありがちなパターンは、
「売上は○○万円、利益は○○万円、現預金残高は○○万円…」
といった数字の読み上げで終わってしまうケースです。
数字の羅列は事実を伝えるだけで、相手に安心感や信頼感を与える材料にはなりにくいものです。
金融機関が求めているのは、数字の裏にある**「ストーリー」**です。
例えば、
-
主力商品の販売単価を引き上げた結果、粗利率が改善した
-
新規顧客の獲得により売上が前年同月比15%増えた
-
仕入先の見直しで固定費を年間300万円削減できた
このように、数字の変化を「具体的な取り組み」とセットで説明することで、金融機関の信頼を得やすくなります。
【4. 金融機関が安心する“見える化資料”が不足している】
口頭で説明するだけでは、金融機関担当者の記憶に残りにくく、金融機関内審査でも判断材料として弱いものになってしまいます。
そこで有効なのが、**「見える化資料」**です。
例としては、
-
売上・利益・資金残高の推移をグラフ化
-
今後6か月の資金繰り表
-
主要取引先の売上構成表
-
借入金の返済計画表
特に資金繰り表は、金融機関との信頼構築に大きく貢献します。
現金残高の推移が一目でわかる資料は、「資金管理ができている会社」という印象を与えるからです。
【5. 面談の“目的設定”が曖昧なまま臨んでいる】
金融機関との面談は、単なる情報交換ではなく、会社にとっての交渉の場です。
しかし、目的が曖昧なまま臨むと、相手の質問に受け身で答えるだけで終わってしまいます。
例えば、
-
運転資金の融資枠を増やしたい
-
金利引き下げを打診したい
-
返済期間の延長を相談したい
このような目的が明確であれば、それに沿った説明資料や話の順序を準備できます。
面談前に「今回のゴールは何か」を整理し、経理担当者や顧問税理士と共有しておくことが重要です。
【6. 改善のための3つのステップ】
-
未来志向の資料を準備する
-
資金繰り表、売上予測、事業計画書を作成し、根拠を説明できるようにする
-
-
数字を経営者の言葉に翻訳する
-
数字の変化の要因と対策をまとめ、短く明確に話せるよう練習する
-
-
面談の目的とシナリオを作る
-
面談で何を得たいのかを明確化し、それに沿って話の流れを構成する
-
【まとめ】

社内経理が万全でも、金融機関との面談でうまく話が進まない理由は、
「過去情報と未来情報のギャップ」
「数字の意味を経営者が説明できない」
「見える化やストーリーが不足している」
といった点にあります。
金融機関は、**「この会社は今後も安定して返済できるか」**を判断したいのです。
そのためには、未来を見据えた資料と、数字を根拠づける説明、そして明確な面談目的が欠かせません。
経理体制の強みを活かしながら、金融機関が求める情報を的確に提示できれば、面談は交渉のチャンスに変わります。