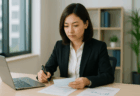目次
はじめに
会社経営において「資金の置き場所」をどうするかは重要なテーマです。売上入金や支払資金を一時的に置いておく「普通預金」と、一定期間引き出さないことを前提にする「定期預金」では、適用される金利が大きく異なります。
しかし「なぜ普通預金の金利はほとんど付かないのか」「なぜ定期預金の方が高いのか」といった疑問については、実務に携わっていても詳しく理解していないケースも少なくありません。
本記事では、普通預金と定期預金の金利がどのように決まるのか、その背景にある金融機関の仕組みや金利政策との関係を整理し、経営者や経理担当者が資金管理に活かせる視点を解説します。

預金金利の基本構造
普通預金とは
普通預金は、入出金の自由度が高い預金口座です。日々の売上入金や経費支払いなど、資金の出入りが頻繁な会社の「資金の受け皿」として使われます。
金利は低く設定されているのが一般的です。これは、いつでも引き出せる資金に対しては金融機関が長期的な運用をしにくいというのが理由の一つに挙げられます。
定期預金とは
定期預金は、預け入れ期間(例:6か月、1年、3年など)をあらかじめ決めて資金を預ける口座です。満期まで解約しないことを前提とするため、金融機関は比較的安定的に資金を運用でき、その分を預金者への利息として還元します。そして、預け入れ期間が長いほど、定期預金金利は高く設定される傾向にあります。
金利は普通預金よりも高めに設定されるのが一般的ですが、市場金利や金融政策の影響を受けます。
金利の決まり方:3つの視点
預金金利の決定には、次の3つの要素が大きく関わっています。
1. 日本銀行の金融政策
日本の金利の大枠は、日本銀行が実施する金融政策によって決まります。
特に「政策金利(無担保コール翌日物金利誘導目標)」が基準となり、これが引き下げられると市場全体の金利も低下し、預金金利も下がります。
逆に、インフレ抑制のために政策金利が引き上げられると、金融機関同士の資金調達コストが上昇し、預金金利も徐々に上がる傾向があります。
2. 金融機関の資金調達コストと運用方針
金融機関は、集めた預金を融資や債券投資などに運用します。
その際、どの程度の資金をどのように調達するかによって、預金金利が決まります。
- 普通預金は解約自由度が高く、安定資金とは見なされにくいため金利は低く抑えられる。
- 定期預金は満期まで引き出されにくい資金として安定的に運用できるため、多少高めの金利を設定する余地がある。
なお、金融機関ごとに資金需要や融資戦略が異なるため、同じ時期でも定期預金金利に差が出ることがあります。
3. 市場環境と競争状況
市場金利(国債利回りや短期金融市場の金利動向)や、金融機関同士の競争も金利水準を左右します。
たとえば、大手金融機関が低金利に設定している状況でも、地域の信用金庫やインターネット銀行が積極的に資金を集めたい場合、定期預金金利を相対的に高く設定する場合があります。
普通預金と定期預金の金利差の理由
普通預金が比較的低金利の理由
- いつでも引き出せるため金融機関は長期運用できない
- 資金の安定性が低く、貸出や投資に活用しにくい
- 口座維持・決済機能という付加価値を提供しているため、利息より利便性が優先される
定期預金が比較的高金利の理由
- 満期まで預ける前提のため金融機関は安定的に運用できる
- 融資や債券投資など長期資金の原資になりやすい
- 他行との競争で、資金調達の手段として金利を引き上げることがある
経営者・経理担当者が押さえるべきポイント
1. 資金の性格に応じて使い分ける
- 短期的な運転資金や支払資金 → 普通預金に確保
- 当面使う予定のない余裕資金 → 定期預金で金利を享受
このように資金の性格に応じて置き場所を分けることで、効率的な資金運用が可能になります。
なお、もちろん、定期預金金利を享受するのではなく、その他の資金活用方法をする事もあります。
2. 金利動向を定期的にチェックする
金利水準は、金融政策や市場環境によって変動します。
そのため、定期預金を組む際には、資金を1年などの長期で固定して利息を確保するのか、3か月程度の短期にして金利の動きを見極めるのかを判断する必要があります。
3. 金融機関ごとの違いを活用する
同じ定期預金でも、金融機関ごとに金利差があります。特に、地域金融機関やネット銀行は金利面で競争力を打ち出すことがあります。
会社の資金を効率的に活用するためには、複数の金融機関の金利を比較検討する姿勢が重要です。

まとめ
- 普通預金と定期預金の金利差は、金融機関が資金を安定的に運用できるか等の違いによって生まれる。
- 日本銀行の金融政策、金融機関の資金調達戦略、市場環境・競争状況が金利の主な決定要因である。
- 経営者・経理担当者は、資金の性格に応じた使い分けと、金利動向の定期的な確認を行うことが望ましい。
金利は「金融機関が勝手に決めている数字」ではなく、政策や市場と密接に関わっています。そして、最近は、「金利のある世界」になり、数年前と比較して、金利が高くなっている傾向があります。そのため、経営者・経理担当者は、その仕組みを理解し、効率的な資金計画を立てましょう。