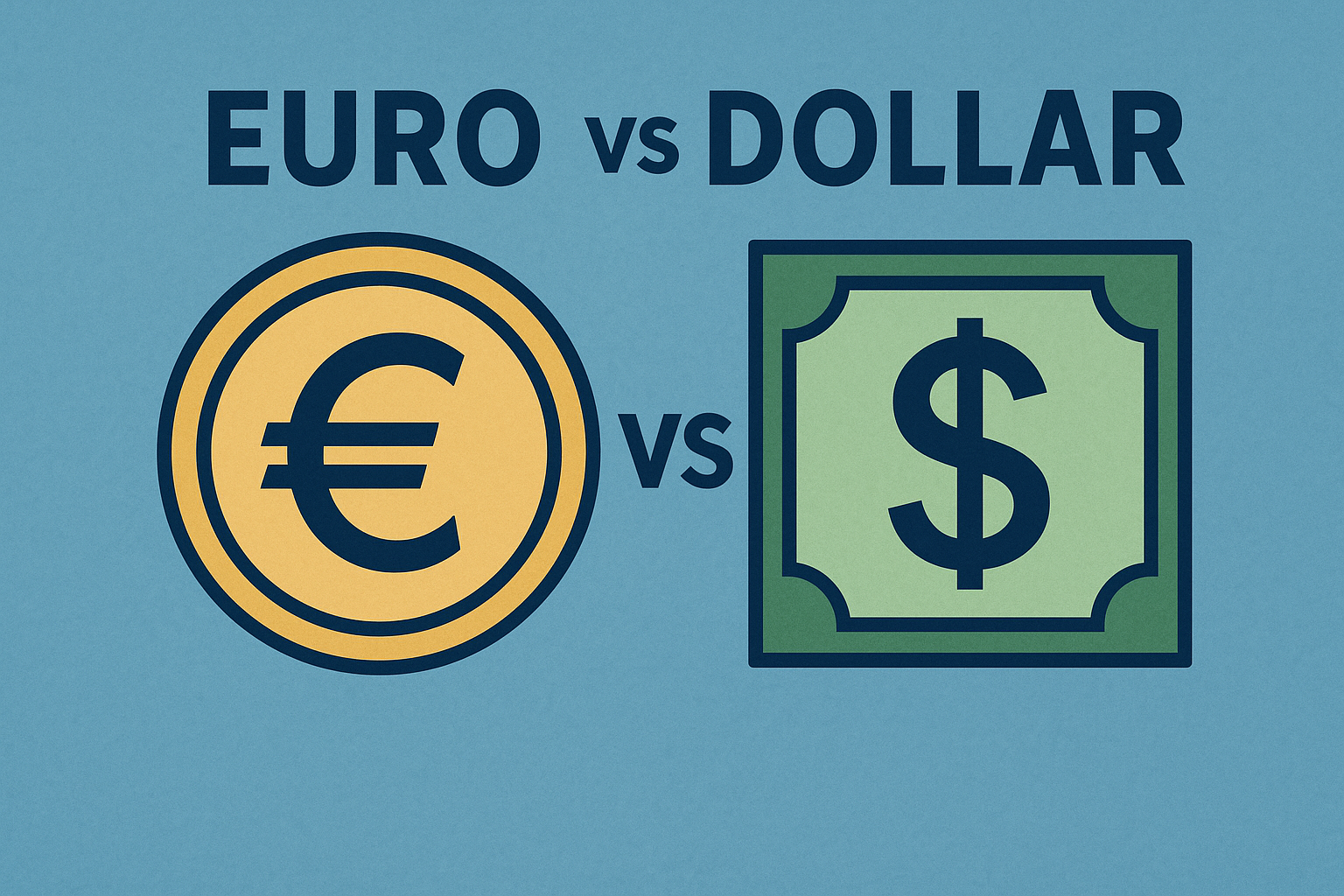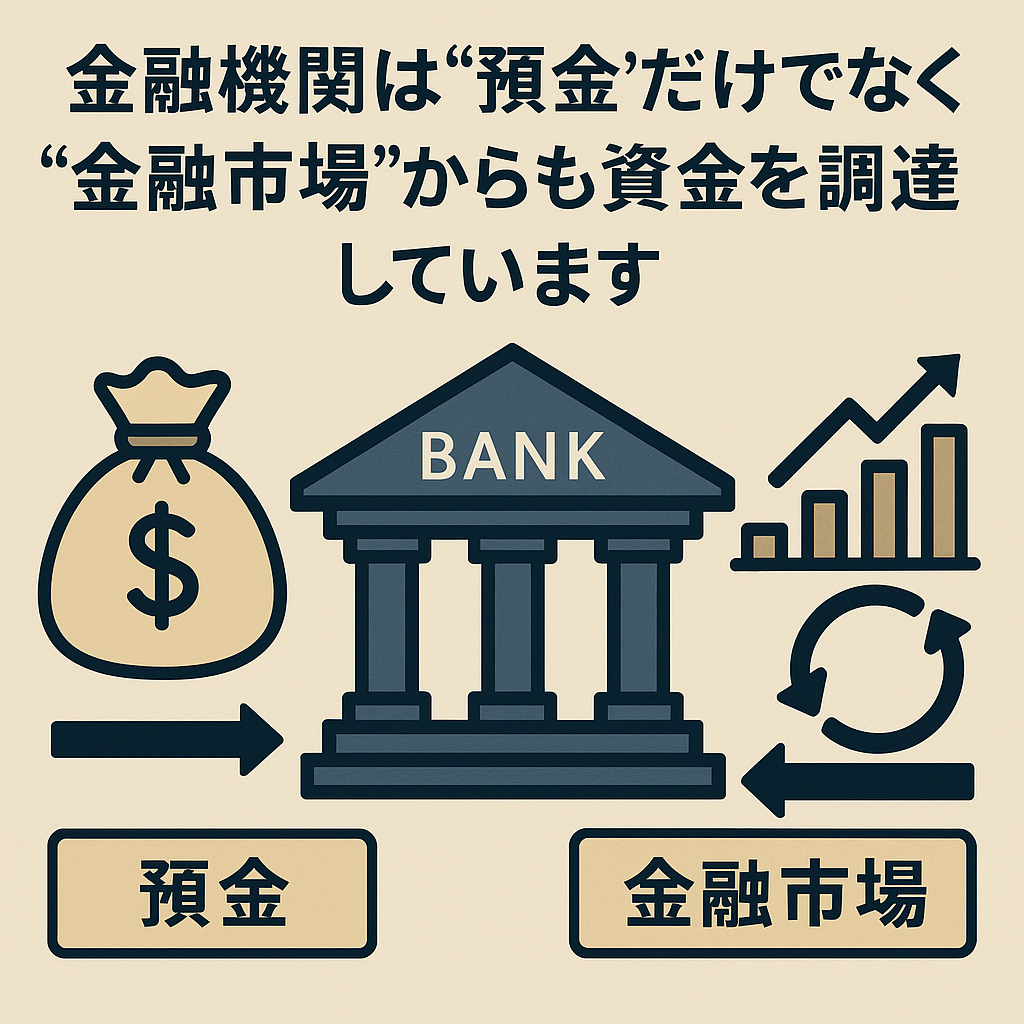目次
はじめに
経営者や経理担当者の方であれば、金融機関から融資を受ける際に
「信用貸し」や「担保貸し」
という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
どちらも「お金を借りる方法」ですが、その性質や金融機関が重視するポイントは大きく異なります。
信用貸しは、会社や経営者に対する“信頼”をもとに実行される融資。
担保貸しは、土地や建物、在庫などの“物的保証”を背景に実行される融資。
同じ融資でも、裏側には「金融機関がどこを見ているか」の違いが存在します。
この記事では、両者の仕組みと違い、経営に与える影響、
そして経営者が押さえておくべき活用のポイントについて詳しく解説します。

信用貸しとは?──会社の信用力に基づく融資
信用貸し(しんようがし)は、
担保や保証人を前提とせず、会社や経営者の信用力に基づいて実行される融資
を指します。
金融機関は「この会社は将来も安定して返済できるか」という視点から審査を行い、
融資の可否を決めます。
信用貸しの特徴
- 担保や保証人を必要としない
- 財務内容や返済能力を重視
- 実績や経営者の資質、取引履歴が評価対象になる
- 金利はやや高めに設定されることが多い
特に中小企業の場合、過去の決算内容や資金繰りの安定性、
そして経営者個人の信用力が大きな判断材料になります。
担保貸しとは?──物的保証を背景とした融資
担保貸し(たんぽがし)は、
土地や建物、在庫、機械設備といった資産を担保に差し入れることで実行される融資
を指します。
金融機関は「返済が滞った場合でも担保を処分すれば貸したお金を回収できる」という安心感を得られるため、融資を実行しやすくなります。
担保貸しの特徴
- 担保(不動産や動産)が必須
- 返済能力とあわせて担保価値を重視
- 金利は比較的低めに設定されることが多い
- 万が一返済不能となった場合、担保資産を処分されるリスクがある
担保を差し入れることで金融機関はリスクを下げられるため、
会社にとっては「金利を抑えて長期の融資を受けやすい」というメリットもあります。

信用貸しと担保貸しの主な違い
ここで、両者の違いを整理してみましょう。
【比較ポイント】
- 融資の根拠
- 金利水準
- 融資枠の広がり方
- 会社にとってのリスク
信用貸しは「会社そのものの信用」に基づきます。
決算内容や経営者の資質、日々の資金管理が評価の対象となり、実績があるほど有利に働きます。
一方、担保貸しは「物的保証」に依存しているため、財務が弱くても資産を持っていれば
融資を受けられる可能性があります。
| 項目 | 信用貸し | 担保貸し |
|---|---|---|
| 融資の根拠 | 会社や経営者の信用力 | 不動産・機械などの物的担保 |
| 金利水準 | やや高めに設定されることが多い | 比較的低めに設定されることが多い |
| 審査の重視点 | 財務内容、収益力、経営者の資質 | 担保価値、換金性、資産の安定性 |
| 融資の自由度 | 無担保で資金調達が可能、経営の自由度が高い | 担保に依存するため、自由度は低い |
| 会社にとってのリスク | 信用失墜により今後の融資が難しくなる可能性 | 返済不能時に担保資産を失うリスク |
| 適した資金需要 | 運転資金や短期的な資金調達 | 設備投資や長期的な資金調達 |
金融機関が重視する視点
金融機関は、融資を検討する際に次の2つの観点を持っています。
- 返済可能性(キャッシュフロー)
信用貸しでは特に重視されます。会社の収益力や資金繰りの安定性がポイントです。 - 回収可能性(担保価値)
担保貸しで重視される観点です。不動産や機械など、換金性のある資産が 担保に差し入れられるかが判断されます。
つまり、信用貸しは「人と会社への信頼」、担保貸しは「物的保証による安心感」というイメージに
近いという見方もあります。
経営に与える影響
信用貸しを受けられる状態は、会社の信用力が金融機関に認められている証です。
これは「無担保で借入できる」という経営上の自由度を意味します。
特に、将来の投資や短期的な運転資金ニーズに対応しやすくなります。
一方、担保貸しは資産を差し入れる必要があるため、万が一返済が滞れば
事業継続に影響を及ぼすリスクがあります。
ただし、信用貸しに比べて金利が低い場合が多いため、
資金調達コストを抑えたい会社にとっては有効な選択肢になります。
活用のポイント──どちらを選ぶべきか?
経営者として重要なのは、信用貸しと担保貸しを「どちらが良い悪い」と単純に比較するのではなく、
状況に応じて使い分けることです。
- 信用貸しが適するケース
短期の運転資金や信用力を高めたい局面。金融機関との信頼関係を築く場面。 - 担保貸しが適するケース
長期の設備投資や大規模な資金調達を行う局面。金利を抑えて返済計画を立てたい場合。
また、信用貸しを受けられる会社であっても、将来の金利負担を考慮すれば
担保貸しを選んだ方が合理的なこともあります。
重要なのは「会社の資金需要とリスク許容度」を見極めることです。
信用貸しを引き出すために必要なこと
信用貸しは、金融機関から「この会社は信頼できる」と評価されて初めて成立します。
そのためには次のような取り組みが欠かせません。
- 月次試算表をタイムリーに提出し、数字の透明性を示す
- 資金繰り表を整備し、将来の返済計画を明確にする
- 金融機関との面談では、数字だけでなく経営方針も説明できるようにする
- 会社と経営者の信用情報を毀損しない(延滞や滞納を避ける)
こうした積み重ねが、無担保でも融資を受けられる“信用力”を育てます。
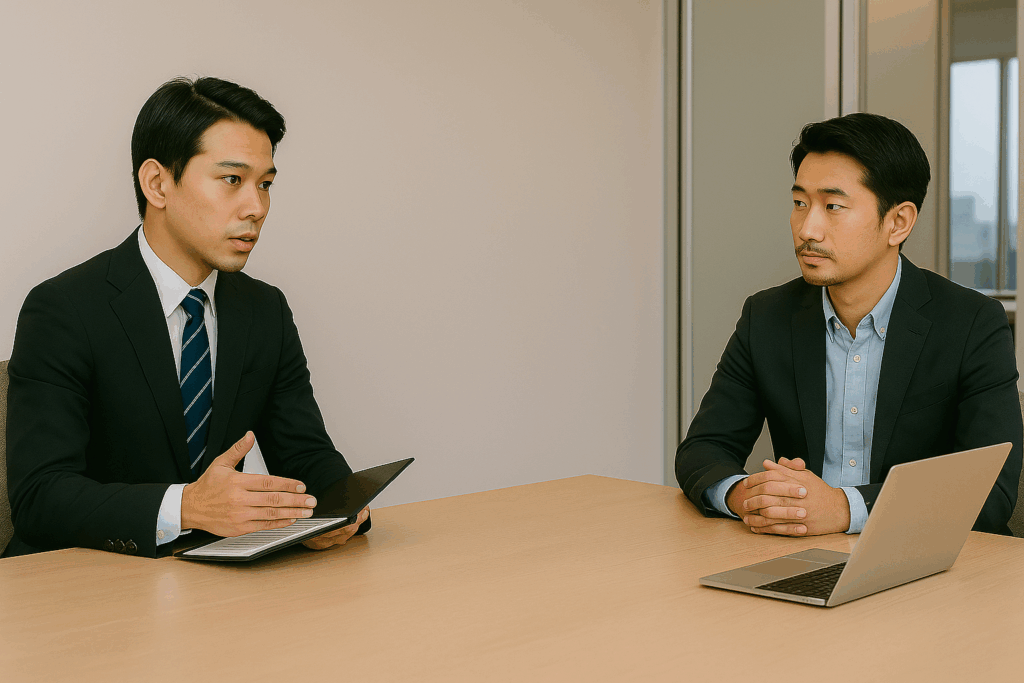
まとめ
信用貸しと担保貸しは、どちらも資金調達の手段ですが、その成り立ちと金融機関の評価軸は異なります。
- 信用貸し=信頼に基づく融資。会社の信用力が試される
- 担保貸し=物的保証に基づく融資。資産を背景に融資が可能になる
経営者としては、自社の状況や資金需要を冷静に分析し、どちらの融資形態が適切かを選ぶことが大切です。
さらに、信用貸しを受けられるように会社の信用力を高める努力は、
長期的に見て資金調達の幅を広げる大きな武器となります。
金融機関が見るのは「数字」と「担保」だけではありません。
日々の経営姿勢や資金管理の精度こそが、将来の融資環境を決めるのです。