
目次
1. はじめに
会社を経営していると、必ず向き合うのが「資金繰り」と「投資判断」です。
特に金融機関とのやり取りや資金調達の場面では、
**「運転資金」と「設備資金」**
という2つの言葉が頻繁に登場します。
「なんとなく違うのは分かるけれど、具体的にどう区別すればいいのか?」
「金融機関は何を基準に見ているのか?」
この疑問を整理しておくことは、自社に適した融資を受けるために欠かせません。
本記事では、運転資金と設備資金の違いをわかりやすく解説し、業務に役立つポイントをご紹介します。
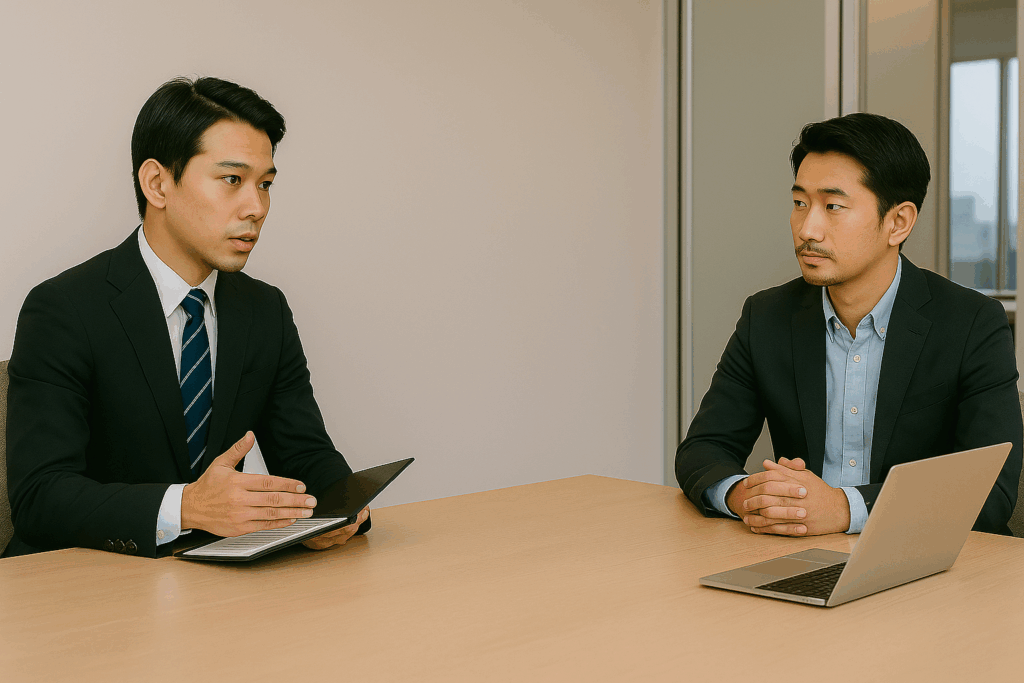
2. 運転資金とは?──日々の事業活動を回すためのお金
運転資金とは、会社が日常的な事業活動を継続するために必要となる資金を指します。
(1)具体例
- 仕入代金の支払い
- 人件費(給与・賞与)
- 家賃や水道光熱費
- 販売促進費や広告宣伝費
- 税金や社会保険料の納付
(2)運転資金の特徴
- 繰り返し発生する(毎月発生する経費や仕入代金など)
- 支出と収入のタイムラグがある(例:先に仕入代金を支払い、売上代金の入金は後)
- 多額な場合と少額な場合があるが、継続的に必要となる
たとえば「仕入代金は翌月末払い」「売上代金は翌々月入金」といった条件だと、
売上が計上されていても、手元資金は一時的に不足します。
このギャップを埋めるのが運転資金の役割です。
3. 設備資金とは?──成長や効率化のための投資資金
設備資金とは、会社が長期的な成長や効率化を目的として投資する際に必要となる資金を指します。
(1)具体例
- 工場や店舗の新設・改装費用
- 機械装置の購入費
- システム導入費
- 車両や大型備品の取得費
(2)設備資金の特徴
- 一度にまとまった金額が必要になる
- 投資後は長期的に回収していく(減価償却を通じて数年かけて費用化)
- 成長や効率化につながるため、将来の利益増加を見込んで支出する
例えば、
「新しい製造ラインを導入して生産性を上げる」
「店舗を拡大して売上を伸ばす」
といった場面で必要となります。
4. 融資における違い──金融機関の視点
金融機関に融資を申し込む際、運転資金と設備資金は以下のように扱いが異なります。
(1)運転資金の融資
- 融資期間:通常は1年以内の短期融資が多い傾向がある
- 返済原資:売上代金の回収を前提
- 金利:設備資金よりやや高めになることが多い
金融機関は「売掛金の回収可能性」や「資金繰り表での返済見込み」等をチェックします。
(2)設備資金の融資
- 融資期間:耐用年数に応じた中長期融資(3~10年程度)
- 返済原資:投資によって生み出される利益
- 金利:運転資金より低めに設定される場合もある
金融機関は「投資による収益改善効果」「回収可能性」「自己資本の割合」等をチェックします。
5. 経営判断に直結するポイント
(1)運転資金は“会社を守る資金”
運転資金が不足すると、給与や仕入代金の支払いが滞り、会社の信用を一気に失います。
売上が順調でも資金ショートすれば倒産する可能性があります。
そのため、運転資金は「会社を守る資金」と位置付けられます。
(2)設備資金は“会社を伸ばす資金”
設備投資は競争力を高め、長期的な成長を実現する手段です。
ただし、投資効果が不十分だと資金繰りを悪化させるリスクもあります。
したがって設備資金は「会社を伸ばす資金」と位置付けられます。
(3)両者のバランスが重要
- 運転資金が不足しないようにすること
- 設備資金は無理のない返済計画で投資効果を確実にすること
このバランス感覚が、安定した資金繰りと健全な経営に繋がります。
6. 実務での整理方法
経営者・経理担当者が実務で混同しないためには、以下のように整理するのがおすすめです。
- 資金用途を明確にする
「日常の支払いに必要か」「将来の投資に必要か」で区分する。 - 返済原資を確認する
運転資金=売上の入金、設備資金=投資による利益。 - 金融機関との説明を明確にする
資金使途が曖昧にならないよう、明確に区別して説明することで、融資審査がスムーズになります。

7. まとめ
- 運転資金:日常的な資金繰りを支える“会社を守る資金”
- 設備資金:成長や効率化に向けた“会社を伸ばす資金”
両者の違いを理解し、金融機関への説明や資金計画に活かすことが経営の安定につながります。
経営者や経理担当者にとっては、資金の性質を見極めて、
必要に応じて最適な調達手段を選択することが不可欠ですので、
資金不足によるリスクを回避し、迅速に、かつ、正確に、成長のための投資判断をしましょう。





