
目次
はじめに
ガソリンスタンドの価格表示には、「ガソリン税」「軽油税」などの文字をよく目にします。
しかし、それぞれの税金がどのように課されているのか、そして消費税との関係はどうなっているのかを正確に理解している方は多くありません。
特に、「ガソリン税の上にさらに消費税がかかっている」と聞くと、「二重課税ではないか?」と疑問を抱く方も少なくありません。
この記事では、ガソリン税と軽油税の違いを整理しつつ、消費税との関係をわかりやすく解説します。
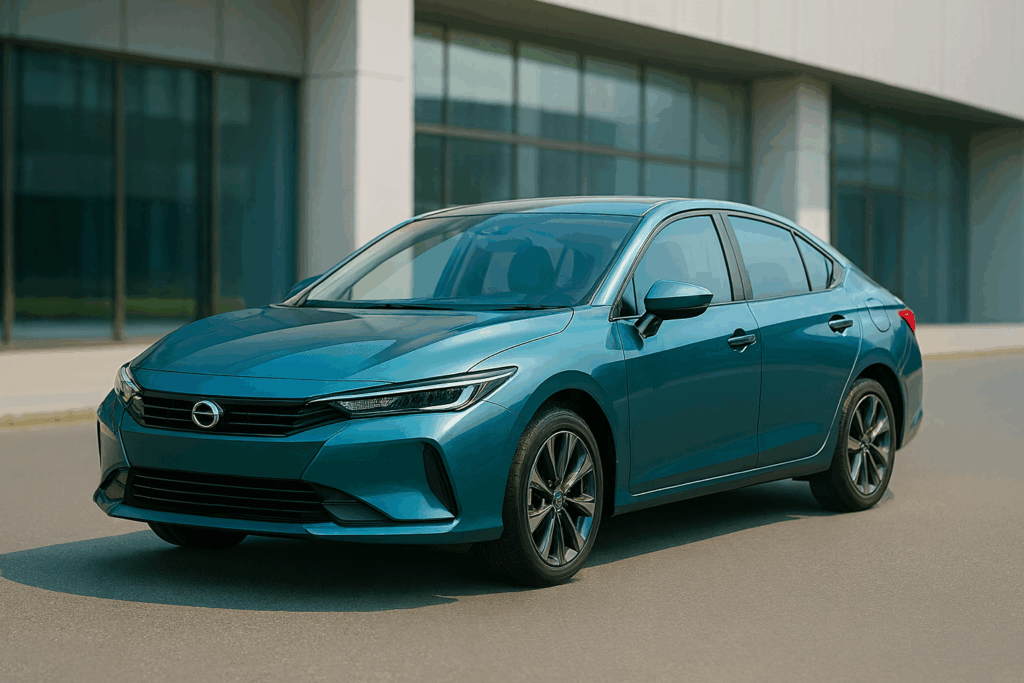
1. ガソリン税と軽油税の基本構造
ガソリン税とは(揮発油税+地方揮発油税)
「ガソリン税」は、正式には次の2つの税金を指します。
- 揮発油税(国税)
- 地方揮発油税(地方税)
この2つをまとめて一般に「ガソリン税」と呼びます。
課税はガソリンの製造業者や輸入業者に対して行われますが、最終的には販売価格に転嫁され、消費者が負担する仕組みになっています。
軽油引取税とは(地方税)
一方の「軽油税」とは、正式には軽油引取税を指します。
これは地方税(道府県税)で、次のような特徴があります。
- 元売業者又は特約業者から現実の納入を伴う軽油の引取りを行う者に対して課税される
- 課税主体は都道府県
- 課税標準は「引き取った軽油の数量」
つまり、ガソリン税が国と地方にまたがるのに対し、軽油引取税は地方単独の税です。
2. 税率の違い(1リットルあたり)
2025年11月現在の標準的な税率は以下のとおりです(暫定税率を含む)。
| 区分 | 税目 | 税率(1リットルあたり) |
|---|---|---|
| ガソリン | 揮発油税 | 48.6円 |
| ガソリン | 地方揮発油税 | 5.2円 |
| 軽油 | 軽油引取税 | 32.1円 |
3. ガソリン税と消費税の関係
ガソリン価格には消費税が課される
ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税)は、商品価格の一部として扱われます。
したがって、ガソリンスタンドで販売されるガソリン価格には、次のように消費税が課されています。
例:
本体価格100円+ガソリン税53.8円=課税標準153.8円
消費税(10%)=15.38円
→ 支払総額169円(概算)
このように、ガソリン税を含めた総額に対して消費税が課されているため、「二重課税では?」という声が上がるのです。
なぜ「二重課税」ではないのか
法的には、ガソリン税と消費税は課税対象が異なります。
- ガソリン税:物品そのものに対する間接税
- 消費税:一定の消費に対する取引税
消費税法では、課税標準を「課税資産の譲渡等の対価の額」と定めています。
この「対価の額」には、他の間接税(揮発油税や酒税など)も含まれるため、形式上は二重課税ではありません。
4. 軽油税と消費税の関係
軽油引取税は消費税の課税対象外
軽油引取税(軽油税)は、**消費税の課税対象外(不課税取引)**です。
つまり、軽油を購入する際に、基本的に軽油引取税の部分には消費税がかかりません。
国税庁タックスアンサーNo.6313においても、次のようにあります。
~
~これに対して、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税は、利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金または立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には、課税標準には含まれないことになります。
~
したがって、軽油価格の構成は次のようになります。
・軽油の本体価格部分 → 消費税の課税対象
・軽油引取税部分 → 消費税の課税対象外
なお、その税額に相当する金額を明確に区分していない場合には、課税標準に含まれることになります。
ただし、同タックスアンサーでも下記記載のとおり、一部例外があります。
~
これに対して、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税は、利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金または立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には、課税標準には含まれないことになります。
なお、その税額に相当する金額を明確に区分していない場合には、課税標準に含まれることになります。
(注) 軽油引取税は、その特別徴収義務者である特約店等が販売する場合(特約店等からその販売委託を受けてサービス・ステーション等が販売を行う場合を含みます。)は課税標準に含まれませんが、特別徴収義務者に該当しないサービス・ステーション等が販売する場合には、課税標準から軽油引取税を控除することはできません。
軽油の価格構造の具体例
例:
軽油本体価格100円+軽油引取税32.1円
→ 消費税の課税対象は本体100円のみ
→ 消費税10円
→ 支払総額142.1円(概算)
このように、軽油税についてはガソリン税と異なり、二重課税の構造にはなっていません。
※先述のように、一部例外があります。
5. 会計・経理実務での扱い
ガソリン購入時の仕訳例
ガソリン購入代金には消費税が含まれています。
したがって、次のように処理します。(税抜経理の場合)
(借方)燃料費 ×××円
(借方)仮払消費税 ×××円
(貸方)現金・預金 ×××円
ガソリン税は本体価格に含まれる間接税であり、消費税の仕入税額控除の対象には間接的に含まれる扱いとなります。
軽油購入時の仕訳例
軽油引取税部分は不課税であるため、消費税の仕入税額控除対象は本体価格部分のみです。(税抜経理の場合)
(借方)燃料費 ×××円
(借方)仮払消費税 ×××円
(貸方)現金・預金 ×××円
領収書上では「軽油引取税」が明示されていることが多いため、
仕入税額控除の際は課税対象部分と不課税部分を区分して処理するのが望ましいです。
※先述のように、一部例外があります。
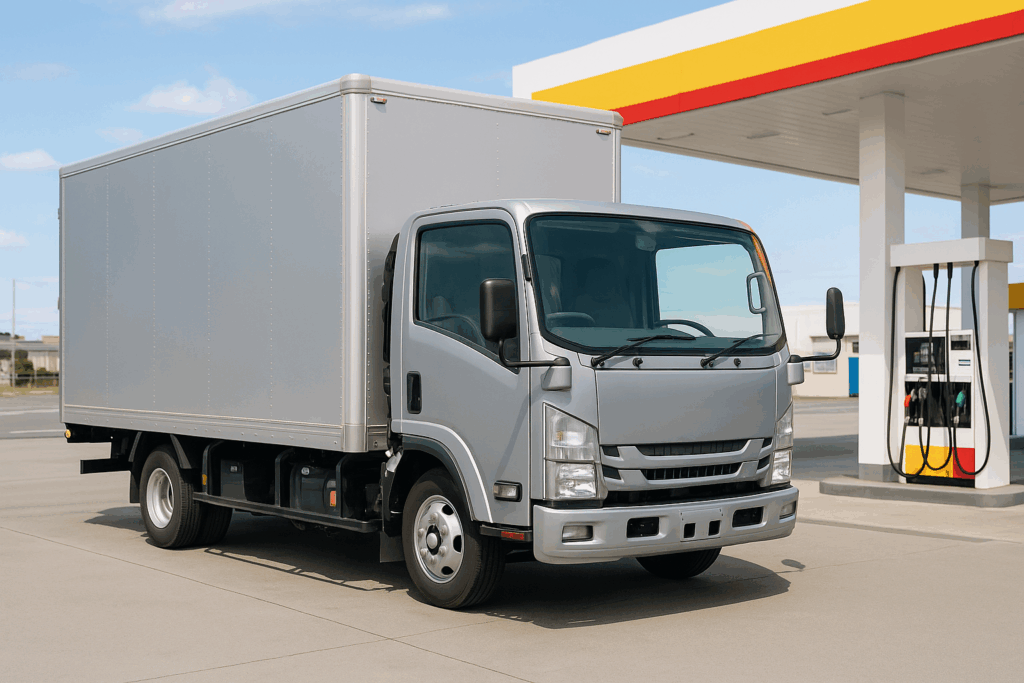
6. まとめ
| 区分 | 税目 | 消費税課税の有無 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 揮発油税・地方揮発油税 | 課税される | ガソリン税部分にも消費税が課される(本体価格+ガソリン税に消費税が課税) |
| 軽油 | 軽油引取税 | 課税されない(不課税) | 軽油引取税部分は消費税の課税対象外(一部例外あり) |
ポイントまとめ
- ガソリン税は「ガソリン税に消費税」がかかる構造(法的には二重課税ではない)
- 軽油引取税は不課税のため、消費税は本体部分のみに課される
- 経理処理では、軽油税部分を不課税として区分する必要がある(一部例外あり)
免責事項
本記事は、2025年11月時点の法令・通達・国税庁タックスアンサー等に基づく一般的な情報提供であり、特定の会社・事案に対する税務判断を示すものではありませんので、最終的な取扱いの判断は、所轄税務署または専門家にご確認ください。
実務で役立つ関連記事
・経営者・業界関係者の方むけ:軽油税の仕組みと“暫定税率”の今後──ガソリンだけじゃない、軽油課税の現実とは
・経営者・経理担当者の方むけ:車購入でよく聞く「残クレ」とは?初めての人にもわかりやすく説明します
・【ご注意ください】大型特殊自動車は、固定資産税が課税されます。





