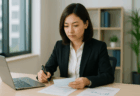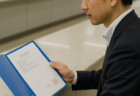目次
はじめに
会社経営の場面で、金融機関との取引は欠かせません。資金をどのように管理・運用し、将来に備えるかは、経営上、重要なテーマです。そのなかで、「定期預金」と「定期積金」はよく耳にする金融商品ですが、実際にどう違うのかを正確に理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。
一見するとどちらも「定期的に資金を預けて利息を得る商品」に思えますが、仕組みや利用目的は大きく異なります。この記事では、定期預金と定期積金の違いを整理し、それぞれの活用方法や経営実務における意義をわかりやすく解説します。

定期預金とは
定期預金は、まとまった金額を一括で預け入れ、一定期間据え置いたのち、元本と利息をまとめて受け取る預金です。たとえば100万円を3年間の定期預金に預けた場合、3年間は基本的に引き出せず、満期時に100万円と利息を一括で受け取る形になります。
特徴としては以下の点が挙げられます。
- まとまった資金を預ける商品
- 満期まで原則引き出せない(中途解約は可能だが利息は普通預金並みに下がる)
- 利息は元本全額に対して計算される
- 運用の安定性が高い
つまり、ある程度まとまった資金を長期間動かす必要がなく、運用の安定性を重視したい場合の手段の一つです。
定期積金とは
一方、定期積金は「毎月一定額を積み立てていき、満期時に元利合計を受け取る」仕組みです。例えば、毎月1万円ずつ、3年間積み立てるといった形で利用されます。
特徴は次のとおりです。
- 少額からスタートできる(毎月数千円~可能)
- 強制的に積立習慣がつく(自動引落しによりコツコツ貯まる)
- 利息は各回ごとの預入額から満期までの期間に応じて計算される
- 将来の支出に備えやすい(教育資金、設備投資、ボーナス原資など)
定期預金が「最初にドンと預ける商品」であるのに対し、定期積金は「コツコツ積み上げていく商品」と表現できます。
両者の違いを整理すると
両者の違いを整理すると次の表のようになります。
| 項目 | 定期預金 | 定期積金 |
|---|---|---|
| 預け方 | 一括でまとまった金額を預ける | 毎月一定額を積み立てる |
| 利息の計算 | 元本全額に対して期間一律 | 各回の積立額ごとに期間計算 |
| 資金の性格 | 比較的余裕資金の運用に向く | 比較的将来の支出準備に向く |
| 向いている人 | 手元にまとまった資金がある人・会社 | 少しずつ資金を貯めたい人・会社 |
| 中途解約 | 可能だが利息が低下 | 原則可能だが条件は金融機関次第 |
このように、目的や状況によって適した商品は異なります。
経営実務での使い分け
中小企業経営や経理実務の現場では、定期預金と定期積金の使い分けが重要です。
1. 定期預金の実務的意義
- 資金繰りが安定していて、余裕資金が生じる場合
金融機関との取引実績作りにもなります。融資の審査では、一定の定期預金残高を確認する金融機関もあります。 - 短期運用での金利優遇
短期の定期預金キャンペーンを利用することで、普通預金よりも有利に運用できる場合があります。
2. 定期積金の実務的意義
- 将来の支出に備える
たとえば3年後に機械設備の更新費用を予定している場合、定期積金で計画的に積み立てれば、満期時に資金が準備できます。 - 経営者自身の給与原資やボーナス資金の準備
事業資金と生活資金を分けて管理する上で、定期積金を利用するケースもあります。
参考:個人家計における使い分けのイメージ
- 定期預金は「余った資金を安全に運用したい」人向け。
- 定期積金は「旅行や教育資金など、将来の目的資金を貯めたい」人向け。
特に家計では「自動的に積み立てる仕組み」が重視されるため、定期積金は“強制的な貯蓄”として有効に機能します。
金利環境と両者の選択
近年まで続いた超低金利時代から転じ、今年は前年と比べて金利が上昇傾向にあるといわれています。定期預金の利息は以前より改善しており、定期積金についても利回りの面で一定の効果が期待できる状況になっています。ただし、それでも投資商品に比べれば大きな利回りは見込みにくいため、依然として「資金管理の仕組み」としての利用価値が中心です。
- 定期預金 → 金利上昇の恩恵を受けやすく、余裕資金を運用しながら金融機関との関係構築にも有効
- 定期積金 → 利息が従来より有利になる一方で、目的資金の準備や貯蓄習慣の形成に引き続き有効
つまり、金利上昇を活かしつつも、資金の性格や管理目的に応じて両者を使い分けることが重要です。

まとめ
定期預金と定期積金は、どちらも「安全に資金を貯める手段」でありながら、仕組みも目的も異なります。
- 定期預金は余裕資金の安定運用や金融機関との取引実績作りに有効とされる
- 定期積金は少額からの計画的な積立に適し、将来の支出準備に役立つ
経営者や経理担当者にとっては、金融機関との関係構築や資金繰り計画の一環として、これらを正しく理解して活用することが重要です。
免責事項
本記事は、一般的な金融知識に基づき執筆したものであり、特定の商品や金融機関を推奨するものではありません。実際の取引にあたっては、必ず金融機関の窓口や専門家にご相談のうえ、ご自身または会社の状況に応じてご判断ください。