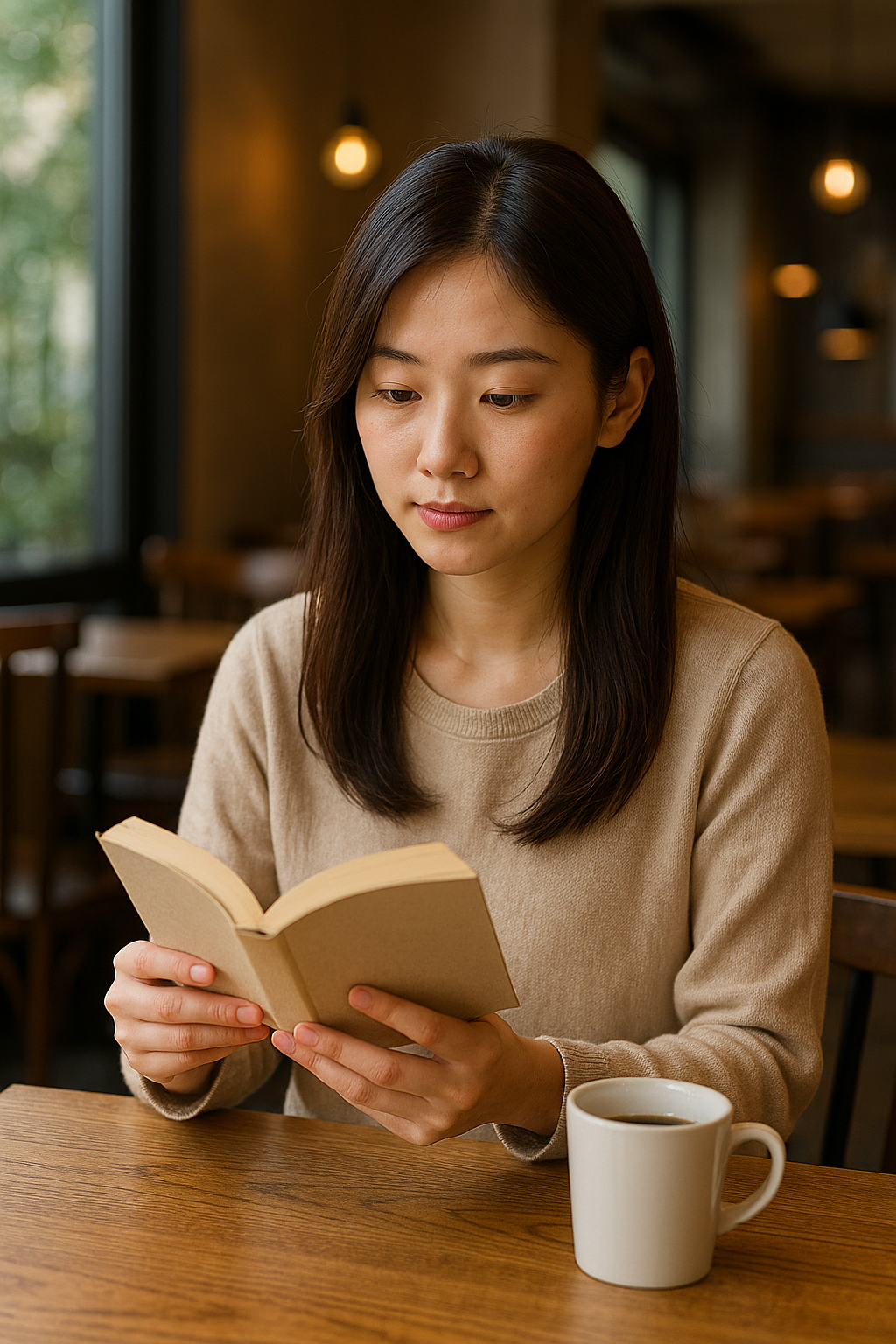
目次
はじめに
書籍の出版や音楽の制作、写真・動画の配信など、さまざまなコンテンツビジネスの現場で耳にする「印税」。
しかし、改めて「印税とはどのようなものか?」と問われると、正確に説明できる人は多くありません。
イメージとして、印税は、著作物をつくった人や権利を持つ人に対して支払われる“対価”であり、作家やクリエイター等にとって重要な収益源です。また、経営者や経理担当者にとっても、印税の仕組みを理解しておくことは非常に大切です。出版やコンテンツ制作の現場と関わる会社にとっては、印税の経理処理や源泉徴収の対応が必須になるからです。
本記事では、印税の基本から、支払われる仕組み、税金との関係、経理上の注意点まで、わかりやすく整理します。

印税とは何か──「著作物の利用に対する対価」
印税とは、「著作物の利用に対して、著作権者に支払われる対価」のことです。
書籍であれば「本が売れた部数に応じて著者へ支払われる報酬」。
音楽であれば「曲が再生・販売された回数に応じて作詞者・作曲者等に支払われる報酬」。
写真であれば「使用料として支払われる報酬」。
つまり印税とは“成果物に対する対価”であり、労働時間とは関係がありません。
これが、給与・請負代金・講演料などの「労務の対価」と異なる大きな特徴です。
印税と著作権の関係
印税を語るうえで欠かせないのが著作権です。
著作権者には、例えば、以下のような権利があります。
- 複製権
- 公衆送信権
- 翻案権
- 譲渡権
- 貸与権
- 上映権 他
これらの権利を、出版社・音楽出版社などに利用させる代わりに支払われるのが印税です。
たとえば、出版社は著者の「出版権」を設定し、本を販売する権利を得ます。その対価が印税であり、販売部数に応じて著者に支払われます。
印税が支払われる仕組み
印税の支払い方法は、メディアごとに異なります。ここでは書籍を例に説明します。
1. 印税率の設定
書籍の場合、印税率は一般的に「定価 × 印税率」で計算され、一般的には、次のとおりとされています。
- 紙の書籍:5%~10%前後
- 電子書籍:30%~70%
※電子書籍の印税率が高いのは、印刷・流通コストがかからないためです。
2. 計算対象となる部数
出版社が流通に出荷した部数ではなく、通常、実際に売れた部数(又は印刷部数)がベースになります。
印税とほかの報酬との違い
印税は「成果物の利用に対する対価」であり、次のの報酬とは税務・経理の扱いが異なります。
1. 講演料
講演に対する報酬であり、印税ではありません。
2. 謝礼(インタビュー・取材協力等)
労務の対価であり、成果物への対価ではないため、印税とは異なります。
3. 監修料
監修の労務提供に対する報酬であり、印税ではありません。
ただし、著作物が利用される形で対価が支払われる場合には、著作権使用料となることがあります。
印税収入のメリット・デメリット
■メリット
- 一度作った作品から長期的に収益を得られる
- 労働時間に依存しない収入(ストック収入)
- コンテンツ資産の蓄積により収益が拡大する場合がある
■デメリット
- 印税率は当初想像していた率ほど高くない事がある(紙の書籍は一般的に5〜10%)
- 通常、入金までの時間が長い
- 税務・契約が複雑な場合が多い
特に、支払時期が半年以上遅れることもあるため、個人事業主や副業作家にとっては注意が必要です。
はじめて印税を受け取る場合は、契約書の内容を理解する
印税率だけでなく
- 出版権設定
- 電子書籍の取り扱い
- 二次利用(翻訳・映像化)
- 支払時期
などを確認する必要があります。

まとめ
印税とは、著作物の利用に対して支払われる「成果物の対価」であり、書籍・音楽・写真・動画など幅広い分野で発生します。印税は、労働時間に基づいて支払われるものではありません。
税務上は、所得の種類等によって取り扱いが変わり、場合によっては、源泉徴収やインボイス制度にも影響します。また、出版社やコンテンツ制作会社にとっては、印税の経理処理や契約内容の理解が欠かせません。
印税ビジネスは、一度作った作品が長期的に収益を生み出す魅力的な仕組みですが、契約上の注意点や税務・経理処理など、押さえるべきポイントも多く存在します。
印税に関しては、今後もその他のテーマでご紹介を致しますので、本記事が、はじめて印税について理解したい方、これから出版やコンテンツ制作に関わる方、経営者・経理担当者・メディア関係者にとって参考になれば幸いです。
■免責事項
本記事は、印税に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の判断等を保証するものではありません。具体的な判断が必要な場合は、必ず専門家へご相談ください。





