
目次
はじめに
「日本の借金は~兆円を超えた」といったニュースを耳にすることがあります。
この「借金」の中心的な存在が、政府が発行する**国債(こくさい)**です。
国債は、国が資金を調達するために発行する「債券」の一種であり、
国家の信用をもとにお金を借りる仕組みです。
しかし、単に「借金」と片づけてしまうと、その本質を見誤ります。
国債は、国の財政を支えると同時に、金融機関や個人投資家の資産でもあります。
つまり、国の借金は、民間の資産でもあるのです。
この記事では、国債の基本構造から、種類、発行の仕組み、そして経済への影響までを整理して解説します。
経営者や経理担当者の方が「金利」や「景気」とのつながりを理解するうえでも、国債の知識は欠かせません。
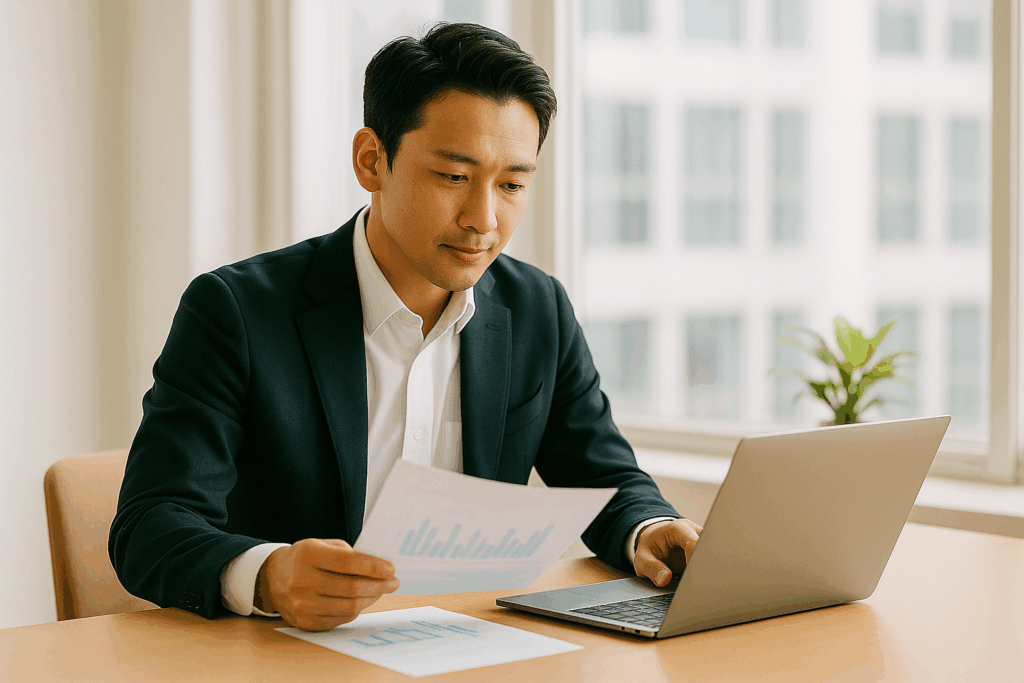
国債とは何か
国債とは、政府が資金を調達するために発行する「借用証書」です。
国は、歳入(税収など)と歳出(公共事業・社会保障など)の差額を埋めるため、
必要に応じて国債を発行します。
国債を購入した人は、国にお金を貸していることになります。
その代わりに、国は一定期間後に「元本」を返済し、
期間中は「利息(クーポン)」を支払います。
この仕組みは、企業が社債を発行して資金を調達するのと似ています。
ただし、国債は「国家の信用」を背景にしており、
民間債券に比べて極めて信用度が高いのが特徴です。
国債の種類と役割
国債には、目的や償還期間によってさまざまな種類があります。
● 一般会計と特別会計の区分
国の予算は「一般会計」と「特別会計」に分かれており、
それぞれに対応する国債があります。
概して、一般会計の赤字を補うために発行されるのが「赤字国債」、
公共事業費などの将来の利益を生む支出に使われるのが「建設国債」です。
● 償還期間による分類
- 短期国債(1年以内)
- 中期国債(1年超5年以下)
- 長期国債(5年超10年以下)
- 超長期国債(10年超)
特に「10年国債」は、日本の長期金利の代表的な指標として利用されます。
日銀の金融政策(長短金利操作=YCC)でも、この10年国債利回りが重要な基準になります。
● 個人向け国債
個人投資家が購入できる国債もあります。
固定金利型・変動金利型などがあり、比較的安全性の高い資産として利用されています。
このように国債は、政府の財政運営のための資金源であると同時に、
金融市場の安定装置という役割も果たしています。
国債が発行される仕組み
国債の発行は、財務省が中心となって行います。
仕組みを簡単に整理すると、イメージとして、次のような流れです。
- 政府が国会で予算を編成
- 歳入不足を補うための国債発行額を決定
- 財務省が国債を発行
- 銀行・証券会社・保険会社などが落札し、購入
- 日銀が市場安定のために買い入れを行うこともある
こうして発行された国債は、市場で取引され、利回りが形成されます。
つまり、国債市場の動き=金利の動きとも言えます。
国債の発行残高は年々増えていますが、
同時に金融機関・保険会社・年金基金・日銀などが安定的に保有しており、
信用リスクが抑えられているのが日本の特徴です。
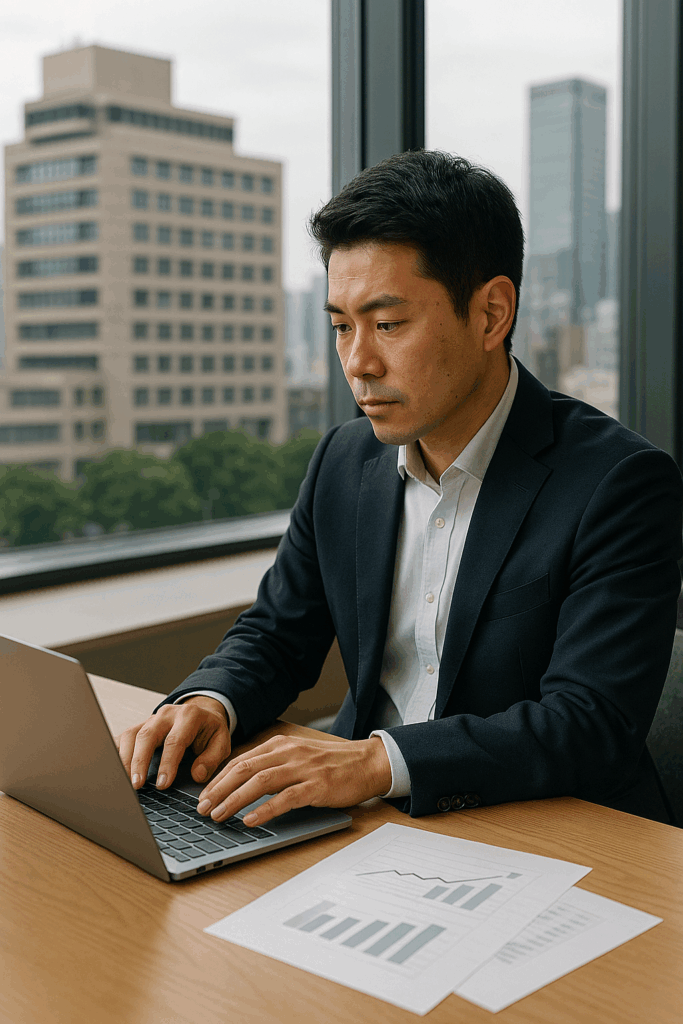
国債が経済に与える影響
国債は、日本経済に大きな影響を与える存在です。
● 金利への影響
国債は金融市場で取引されるため、需給バランスによって価格と利回り(=金利)が動きます。
たとえば「年に1万円の利息がもらえる国債」があるとします。
この国債を10万円で買えば利回りは10%ですが、
人気が出て値段が上がり、12万円で買う人が増えると──
同じ1万円の利息でも、もうけの割合は約8%(1万円÷12万円)に下がります。
このように、国債の価格が上がると利回りは下がるという関係になります。
この利回りの変化が、住宅ローン金利や企業の借入金利にも波及します。
● 財政への影響
国債の利払いは、国の予算の中でも大きな支出項目です。
2025年度予算では、利払い費だけで年間約10兆円規模に上る見込みです。
金利が上昇すれば、これがさらに増加し、財政負担が重くなります。
● 経済刺激の役割
景気が落ち込んだとき、政府は景気を立て直すために「お金を使う」政策を行います。
たとえば、公共工事を増やしたり、給付金を配ったりするようなケースです。
このときの資金をまかなう方法の一つが国債の発行です。
つまり、国債は「景気を支えるための資金源」としての役割も果たしています。
国債のリスクと信頼性
国債は「安全資産」と呼ばれますが、リスクが全くないわけではありません。
● 信用リスク
理論上、国が債務不履行(デフォルト)に陥る可能性もゼロではありません。
ただし、日本は自国通貨建ての国債を発行しているため、
外貨建て債務を抱える国に比べ、リスクは低いとされます。(※)
(※)日本は自国の通貨(円)でお金を借りているため、
必要があれば円を発行して返すことができます。
一方、外国の通貨で借りている国は、自分でその通貨を作れないので、
為替が動くと返済が難しくなることがあります。つまり、自国通貨で借りている日本の方が、返済不能のリスクは低いということです。
● 金利変動リスク
金利が上がると、新しく発行される国債のほうが高い利息になります。
すると、過去に発行された“利息の低い国債”は魅力が下がり、
その分、価格(売値)が下がるという仕組みです。
これにより、投資家にとっては一時的に評価損が出ることもありますが、
満期まで保有すれば元本と利息はきちんと受け取れるため、
長期的には安定した資産として利用されています。
● インフレリスク
物価が上がると、同じ金額でも買える量が減るため、お金の実質的な価値は下がります。
これは、固定金利で利息が決まっている国債にも影響します。
将来受け取る利息や元本の「購買力」が下がってしまうのです。
そのため政府は、物価が上がると利息や元本も連動して増える「インフレ連動国債」を発行し、
投資家の価値目減りを抑える仕組みを整えています。

まとめ
国債は「国の借金」であると同時に、私たちの預金や年金などを支える仕組みでもあります。
財政赤字という言葉ばかりが取り上げられがちですが、
実際には、国債がお金の流れを円滑にし、金利や景気を安定させる役割を果たしています。
また、国債の金利が動けば、会社の借入金利や設備投資の判断にも影響します。
つまり、国債市場を理解することは、経営判断の精度を高めることにつながるのです。
免責事項
本記事は、2025年10月時点の公表情報および財務省・日本銀行・内閣府などの資料を参考に執筆しています。
内容は一般的な情報提供を目的としており、投資・融資・経営判断の結果を保証するものではありません。
最終的な判断は、最新の公式情報および専門家の助言に基づいて行ってください。
実務で役立つ関連記事
・経営者・経理担当者の方むけ:定期預金と普通預金の金利の決まり方の基本を押さえましょう
・経営者及び経理担当者の方むけ:債券市場とはどのような市場なのか
・経営者及び経理担当者の方むけ:中小企業がチェックしておきたい「国債利回り」の動向と金融機関の融資スタンス





